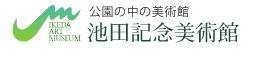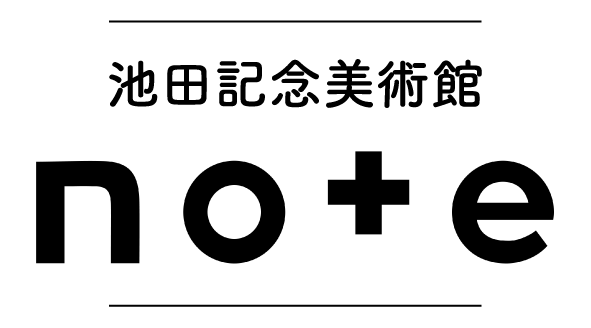6月初旬、海發準一さんから極上エッセイ7本が突然、八ヶ岳の麓からメールでとどきました。海發さんは小千谷市出身。八ヶ岳のアトリエで薪割りをしながら、コトバを紡ぎ、磨いていたのですね。
(池田記念美術館・高橋)
エッセイ①
八ヶ岳南麓に引っ越したのは、自力でアトリエを建てるのと
折しもの出版不況が重なった6年前。
中之島の共同アトリエを出たのは約30年前だから、随分遠回りしたなぁというのが本音だ。
アトリエを建てる喜びというより、今ここで動かなければ二度と生きた人生は巡ってこないだろうという強迫観念とも予感がした。
インターネットの普及は予想より遅かったけど、これがなければ山の中でデザイン仕事(金は稼がないと)できないからね。
日本の構造改革は遅いですな、それでも、なんとか間に合ったけど。
結局この30年間、映画一本つくるので精一杯、最後のリニア編集かも。
映画には表現者としての自己同一性にこだわりもなく、
ファンとしてブラザーズクエィのスタイルを真似て15分の映画を作ったものの、
徹夜の連続で満足の出来とはいかず、
関係者からの「君は日本のブラザーズクェイだ」という言葉を最大の賛辞と受け取り、今もそのまま。
良いアイデアあるから、できればもう一本撮りたい。
あの頃、同級生だった大学生や高校生はどうしていることやら?
自殺した子もいるけど、プロの映画監督になったのは棚田入月だけかな?
いつの時代も若者は不安定で悩んでいた。悩みの大きさは同じ、ただ対象や状況が違うだけ。
映像の仕事をしてる人も他にいるだろうけど、この世界は資本や人間関係など現代美術界より大変だし、実験映画となるとなおさらだ。
高橋さんも自分も今日まで決して平坦だったとは言い切れない七転び八起き、
七転八倒じゃなくて良かったけど。
銀座の大衆酒場「八起き」ってまだあるのかな?
そんなわけじゃないけど、なぜだか八並びの
八ヶ岳、八海山、八色。
小学生から高校まで校歌には必ず八海山が詠まれていたね。
大人になってからは謳わずに飲んでばかりだけど。
「八」は末広がりで縁起が良いし、沢山という意味もある。
美術家主導の大規模展覧会って、そうはないだろう?
初年度は30人だけど、こりゃ80人か88人になったりして!
八百万の美術家が集まり、大酒宴開く大きなイベントめざします。
馬鹿囃子(関東近辺では昔から名もないお囃子をそう呼んだ)で飲んで踊り、
秋の魚沼は「八色の美有月」と呼ばれるかも。
エッセイ②
春山の美しさは殊の外で、絵描きなら(特に日本画)絵の主題になりますが、
ブナやナラの新緑の芽吹きと山桜の淡いピンクが、春霞みに生きる喜びと生命の力強さを感じます。
そして日一日と緑が深くなり、緑の濃淡が山に奥行きや深みを与えます。
と、ここまでは普通。
この春山の淡い美しさと緑の濃淡による奥山が作り出すその間に、1日か2日特別な日があることを今年発見しました。
いやーびっくり。
近頃絵画を語るに、一般的には死語となりつつある「バルール」が、我々には語られます。
「バルール」とは普通は「色価」と訳されるけど、ちょっとわかりにくい。明度と濃淡だけとも違う。
色と色の関係から、その相関関係から生まれる平面上の空間位置やバランスのことなのだが(異論あるかも)。
とにかく色により位置が生まれる。
「バルールがあっている」とか「バルールがくずれている」とか言うわけです。
自然界では、平面とは違って実際の空間・奥行きがあるわけだから、自然界でバルールが狂っていることはありえない。
空間は距離で実在する、賑やかで猥雑な都会はそれはそれでバルールが合っている。
文教地区に、どぎつい看板や風俗があればバルールは合わないわけです。
にもかかわらず、1日か2日は、星新一のショートショートじゃないけど、
空からカドミウム・グリーンがべったり降ってきて手前も奥もぜーんぶ同じ色価になる瞬間があった。
実在空間のボナール。三次元の二次元化?
実在するはずの空間が、視覚的には(錯覚だとしても)平面化=空間の均質化して見えます。
そのくらい緑がナマナマしい。光もあるし条件が厳しいかもしれない。
それと老眼が酷くなったか? 衰えた視覚の錯覚?
全く奥行きがない緑のカーテンで空間が閉ざされた、摩訶不思議な1日でした。
とてもボナールな風景でした。
エッセイ③
新潟弁(魚沼)では「嘘」を「ゴッド」と言います。
「嘘言わないでください」は「ゴッド言うなて」となります。
あるいは「イ」を「エ」と発音し、「エ」を「イ」とも書きました。
國語元年以前の話ではありません。
しかし「ゴッド」は英語では「GOT」なので「神」です。
新潟では神は「嘘つき」という事になります。
まぁ真理かも。新潟には真理があちこちに偏在しているようです。
これは本当です。
ちなみに「ほんと?」は「ほっけ?=肯定的意味」。法華宗でも魚の開きでもありません。
「うそぉ?」は「うっすぅ?」
やはり越後では信仰心があついのか? 疑り深いのか?
「ほっけ? そういやんだぁ=ほんとに? そういうことなんだ」などと神仏織り交ぜて疑り深いかもしれません。
それから「コッツォネ」や「コテ」などとも言います。
これは「貴方がいう事が正しいです」を「おめさんが、ゆーことが正しいコッツォーネ」という感じ。
でも、もう少し町中の言葉では「おめさんが、ゆーことが正しいコテネ」となります。
いずれにせよ新潟弁はオシャレなイタリア語に似ているわけです。
南か北かでイタリアはヨーロッパとアフリカの違いはあるけど。
あと恥ずかしいことを「しょうしぃ」と言います。長野県は教育県なので「お」をつけて「おしょうしぃ」と言うそうです。
オシッコが漏れたわけではありません。
「トイレは、もう少し先に」などと案内しないように
笑いながら「しょうしぃー」とか「しょうしぃーやー」などと
さきほどのコテと合わさって「しょうしぃーこてや」とも言ったりします。
さらに「とても」を「コッテ」とも「ゴーギ」とも言います。
なので「とても恥ずかしい」は「コッテしょうしテ」になります。
コテコテですね。
町内によっては次男を「オジ」、ご主人を「あんさま」
奥さまを「あねさま」、長男を「あんにゃ」などとも言います。
どんなぐあいですか?は「なじらね?」と言ったりします。時間を聞いているわけではありません。
年頃の可愛い女の子も自分のことは「おれ」だったなぁ。
話し言葉を書き言葉にすると、
「おら、なにゆーてらんだが、いっこわからんくなってきたこて」となりました。
言葉は地域内でも違いますから、
「おめさん、どこんしょだね?」と聞かれるでしょう。
「ちゃーざーむらの隣だこて」と言うことになるでしょう。
エッセイ④
自分が育った小千谷はその昔、魚沼の中心地でした。中心と言っても二市三郡の真ん中にあるのではなく北の端っこ。
そこに地方財閥の西脇家(西脇順三郎の本家)を中心に、地方行政の役所や銀行が集まっていたのです。
小千谷の町は、ほとんど全部西脇家の土地で、皆地代を払っていました。
要するに役人が冬の交通の便を考えると、雪が深すぎて魚沼三郡や十日町には役所を置けなかったのでしょう。
国鉄の工事局もあったし、総合病院が二つ、国立療養所が一つ、伝染病院も伝電の基地局もあった。
税務署もあり面倒くさかった。
当然、花柳界も賑やかで大小の小料理屋や料亭があり、芸者置屋だけじゃなく町外れには赤線青線廃止以前は大きな遊郭もあったわけです。
町は紺屋の染物の匂いに、自動織機のガチャガチャいう音で喧しく、定時制に通う中卒労働者にあふれていましたね。
由美かおるが「信濃川」という映画のロケで小千谷高校と小千谷本町の雁木でロケしたときは、
私たち生徒は授業にはでず自主的に社会科見学したものです。
ちなみに多摩美に入学したら、そこでも由美かおるが自分を待っていました。
「夕陽ヶ丘の総理大臣」?とかいう中村雅俊のテレビだったかな?
母親の実家も含め親戚の機屋三軒は倒産やら廃業で皆止めてしまった。
それでも先日NHKの番組「いっぴん」でよく見た景色だと思いきや、小千谷実家の隣の家じゃん!
お隣の機屋の幼馴染は伝統工芸師となり「小千谷縮」で頑張っているらしい。
小千谷人は変わっていて、凧揚げのタコをイカと言います。
これはワザと言ったのだと思うけど、
上説の賑やかな花柳界と酒ばかり飲んでる旦那衆のせいかもしれませんが「小千谷のイカ=凧」は盃の形です。
盃凧といいます。もうだれも作っていないでしょう。
廃業した新潟で三本にはいる料亭「東忠」の玄関に飾ってありました。
旦那衆はよく酒を飲み、茶道も盛んでした。
お茶をやっていないと旦那衆の仲間に入れない、古い制度が幅をきかせた社会だったのです。
大人になったら芸者さんあげて料亭で楽しい宴会するもんだと思っていたけど、先立つものがありませんね。
変わっていくもの、意図して残していくもの、文化は生き物のようです。
エッセイ⑤
新潟は日本で一番神社が多いと聞きます。
県社は新潟市の白山神社でしょうか?
日蓮や親鸞も佐渡や越後に流されてきたのに神道が多いんですね。
一宮は弥彦神社。
二宮は魚沼神社で(上弥彦神社ともいいます)、小千谷はそれの門前町です。
二宮のほうが創建は古いと聞きます。
信濃川が越後にはいると魚野川や刈谷田川の支流も合わさって
暴れまくり、水田も胸までつかる泥沼だったのです。今も刈谷田川は川底の浅い暴れ川ですが、
超大規模の二重堤防が完成したから洪水になっても、さすがに住民は守られるでしょう。
そんな地の利もあって二宮のほうが古いのじゃないか?
魚沼にはいたるところに十二神社があります。
小千谷にも白山運動公園というところに、廃社になってるけど白山神社がありました。
本殿のあった林は結界とされ、立ち入り禁止だったが今はどうなっただろう?
我が家は白山神社と国分尼寺・五智院の御用鍛冶と伝え聞きます。
本家の従兄弟は新潟で三番目に古い会社起業が自慢でした。
千二百年前だそうな。
江戸時代に、貸鍬・貸鋤で儲けたようです。暖簾分けしなかったんですね。
農業と密接だったので、2月の初午のお祭りは盛大でした。
お稲荷さんに繁盛祈るため
町内中の子供を集めて、ご馳走を振る舞いました。(西脇順三郎がエッセイで子供のころ楽しみだったと)
坊主が来て、なんだか意味不明のお経読んで不気味な祭りだった。
坊主言うに「仏さまとお稲荷さんは仲が良いんだ」と。
その昔の火事で半分焼けた、お稲荷さんの幟や不気味な人形を前に言われても、
お化け屋敷が家の中にあるようなもの。
だいたい、ウチの宗派の坊主じゃないんだけど?
良寛さんと貞心尼じゃないけど、新潟は尼寺が多いです。
安寿様と言いましたが、出家はしたけど正式は僧籍じゃないのじゃないか?(不明)
安寿様が方丈様になられたというのを聞いたことあります。
女性がわけあって剃髪するか? 瞽女になるか?
そこには、辛くて悲しい歴史があるのかもしれません。
神社仏閣が多いのは、それを証明しているのかも。
エッセイ⑥
徳川家康は最後まで上杉を恐れたと伝え聞きます。
遺言で東北封じと関八州の鎮守となるべく日光に分霊された。
魚沼神社は上杉謙信が出兵する際に必ず戦勝祈願したことで有名。
謙信は小千谷のあたりで信濃川を渡ったと聞きます。(別な場所という人もいるし、塩沢にも魚沼神社があります)
だから、小千谷の信濃川川べりの西岸に「二荒神社」が渡らせまいと鎮守しているのか?(ここは日光から見て北辰の方向)
東岸にも小さな別院が幾つか祀られていて用心深い。
春の祭りでは、魚沼神社から天狗がわざわざ二荒神社に挨拶に出向く。
そして追い返される。
江戸時代、小千谷は天領だったり、支配者が変わるけど、上杉移民一揆が恐ろしかったのか?
二荒神社は東北封じと関八州の鎮守。
魚沼神社は天狗と化身して恭順の挨拶が毎年繰り返される。
この祭りを、大きく盛大にすれば良いのに、そうはならなかったのは徳川の呪いか?
その後、戊辰戦争で長岡、会津、桑名残兵が激戦後、ボロボロ越後に入ったが、
軍隊で一番住民に優しかったのは米沢から来た上杉兵だったと。
謙信公の所縁の地、ふるさとにたいして格別の思いがあったと。
小学生のころ、友達と自転車で国道17号を下り信濃川対岸の朝日古戦場に行った。
司馬遼太郎の小説「峠」の現場で、今は整備されているけど当時は山道だった。
山に登ったら等高線にそって塹壕が掘ってあった。
その塹壕の中を歩くと、ところどころ土の色がドス黒く染まっていて、
子供心に、嗚呼ここで人が死んだと直感!
急に怖くなって、泣きそうになりながら駆け出して山を降りた記憶がある。
その怖さを、誰に言うわけでもないのに、
クマが出そうだったから逃げたんだと自分に言い聞かせたのは、
感じた直感があまりにリアルで恐ろしかったからかな?
自分でもわからない。
山岳宗教の修験者は八海山で苦行したあと、
小千谷の湯殿川で身を清め月山に向かったとも。
山形とも縁があったのだろうね。
エッセイ⑦
小千谷と山古志の闘牛が古いのは滝沢馬琴の「南総里見八犬伝」でした。
幼い時分に見た牛は、とても大きくて怖い。
今見ても同じ感想ですが、とにかくすごい。
小千谷の闘牛は牛が大きこと、試合で決着をつけないこと、勢子の人数が多いことが有名です。
人間がやる隠岐の古式相撲も同じ、二番とって二番目は先に勝ったほうが負けて終わる。
狭い社会では暗黙の了解があり、そのことのほうが人生にとってリアルな制度で装置だった。
戦場で名乗りをあげて名誉を懸けている間に、名もない雑兵に槍でブスリというのは日本だけでなく
世界中で起きた戦いの革命・近代化だったようです。
「命を惜しむな、名を惜しめ」などと言ってられません。
保元の乱の言葉と言われているから古すぎるかも? でも、その意味はわかる。
相手がわからないだけ! つまるところ、言葉や価値を共有していない文化外対立なわけです。
少年マガジンで「空手バカ一代」が連載され、折しもブルース・リーの映画の影響もあり、フルコンタクト空手が全盛になりました。
梶原一騎の創作に嘘ばかりと嫌気がさした作画の「つのだじろう」が担当下りて、
次に連載したのが「うしろ百太郎」と「恐怖新聞」。
リアル・フルコンタクト空手より心霊世界のほうが「つのだ」にとってはリアルだったというのが、おかしい。
極真魂は見ていて凄いし、皆真剣。
だけど時代は変わりますね。あれだけ「寸止め空手」とか言って揶揄していたのに、
松濤館、全空連の伝統派空手(守りや捌き主体)がオリンピックの競技に採用されたら、
フルコンやっていた人たちが、全空連の道場で稽古している昨今ですから、隔世の感ありです。
テコンドーって実は松濤館空手から生まれた格闘技、外国人は本当の経緯知らな人が多いですね。
伝統派空手・琉球空手の奥深さと歴史・実力知ったら皆感動すると思います。
型は素晴らしいですよ、早くてカッコイイ! こんな人を襲いたいと思わない。